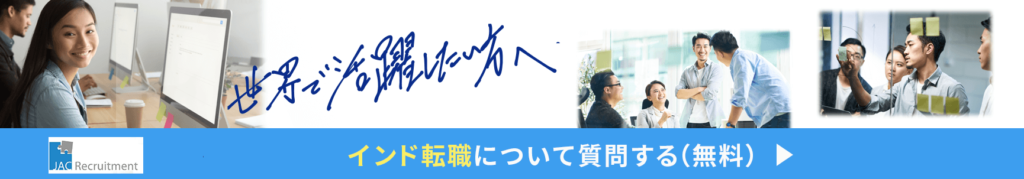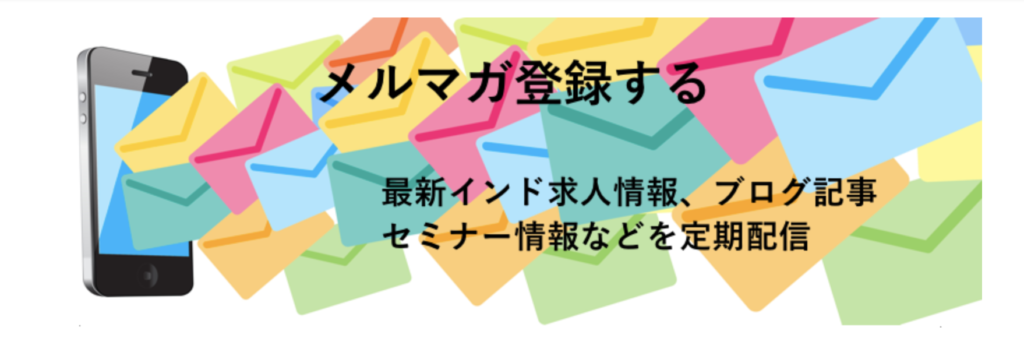「無人島に何か1つだけ持っていくとすれば何を持っていく?」
この質問、人生で15回くらいされますよね。皆さんは何と答えますか?ナイフやマッチ、もしくは携帯電話?本当にいろいろなものを考慮しますよね。そんな中この質問に対して必ずこう答える人がいます。
「水」
この質問は言い換えるなら「あなたが思う、生きていくうえで一番欠かせないものは何?」という意味です。つまり生きていくうえで一番欠かせないものが水だと考えている人がいるということです。確かに命を繋ぐ存在である水は絶対に欠かせないものですよね。
実生活において水の用途は飲料用だけに留まりません。洗濯、料理、シャワーなど本当に多くの場面で水は私たちの生活にかかわってきます。つまり水を安定して供給する整備が行き届いていなければ私たちの生活は一気に不便になるのです。
前回の電気編に続き、今回は水編と題し主に上下水道の整備状況をご紹介します。インドの水に関する整備はどこまで進んでいるのでしょうか。インドの水はガンジス川ぐらい汚いと思う方は是非ご覧ください!もちろん今回もインドとASEANの現状を合わせて紹介します!
インドの水事情

インドの水道水は絶対に飲むな。日本ではもはや通説になっています。筆者も両親からしつこく念を押されました。どうやら日本人はインドの水に対してマイナスの印象を持っているようです。そんな汚そうなイメージのあるインドの水事情を見ていきましょう。
上水道

都市部に関しては上水に関して困ることはありません
まず最初に上水道とは何か、簡単に確認しましょう。上水道とは飲料その他に用いる上水を供給するための水道のことです。また上水とは主に飲用や炊事用、あるいは風呂、トイレ、洗濯といった洗浄などに使用される水のことです。それでは上水道に関する基本情報を見ていきましょう。
| 上水道総延長 | 上水道密度 | 上水道普及率 | 無収水率 |
| 58万㎞ | 0.17 | 80% | 35% |
インドに設置されている上水道管の総延長は58万㎞といわれており、密度(総延長/国土面積)が0.17となっています(日本は1.71)。日本と比較するとかなり低い数値に見えますが、上水道普及率80%というデータが示す通り整備が全く進んでいないというわけではありません。
ただ上水道菅自体の質があまりよくなく、それが無収水率の高さに表れています。無収水率とは、浄水場から配水したものの道管の質が悪いために、どこかで漏れや盗水が発生し料金が徴収できない割合のことです。つまりこの数値が高いということは道管自体の質が悪いということです。インドにおける無収水率は35%となっており日本の7%と比較するとかなり高い数値です。質の面でもまだまだ差があるようです。
ですがご心配なく。グルガオンなどの都市部では上水が不足することはまずありません。シャワーもきちんと出ますし、洗面台も同様です。流し場ももちろん例外ではありません。その理由は不足した時に使用するタンクがあるからです。だいたいどの家庭も断水に備えてのバックアップがしてあるので、不足はほとんど起きません。現地で働く日本人の方が住む場所というのはおおよそ都市部ですから上水に関しては問題なしといってもいいのではないでしょうか。
あえて心配すべき点を挙げるとするならば水質です。水道水はそのまま飲むのはよくありません。上の写真の猫のように飲んでしまうと8割方腹痛が起きます。飲み水はウォーターサーバーや売られているペットボトルの水を購入するようにしましょう。料理用の水に関しても同様です。ただ筆者は歯磨きの時に水道水を使っていますが、特に腹痛が起きたことはありませんので微量であれば大丈夫なようです。生活レベルの水事情に関してはこちらの記事をご覧ください。
インドの上水整備は普及率80%という数データが示す通りある程度進んでいることが分かりました。特に都市部では上水に関して何の問題もなく生活することができるということをご紹介し、安心した方もいるのではないでしょうか。では一方の下水道整備はどこまで進んでいるのでしょう。
下水道

下水道の整備状況を見ていきましょう。下水道とは使用済みの水を流す水道のことです。もし下水道が生活における衛生状況が著しく下がります。上水道と同様に生活には必要不可欠なもので、かつ整備が必要なものです。インドにおける下水道整備の状況を以下の表にまとめてあります。それでは見ていきましょう。
| 下水道総延長 | 下水道密度 (総延長/国土面積) | 下水道普及率 |
| 16万㎞ | 0.04 | 30~40% |
インドの下水道の長さは16万㎞で、密度は0.04となっています。日本の下水道密度は1.24であることから整備状況はかなり遅れているようです。実際に下水道の普及率は30~40%程度といわれています。
多くの公衆トイレは、場所を問わず下水道整備が行き届いておらず水洗式でないトイレがほとんどです。現地のインド人の方が住むようなアパート(集合住宅)も同様です。私が実際にお邪魔したインド人の部屋にはシャワーやトイレがなく、住民は外にある共用のものを利用していました。上下水道の整備が一部屋ごとに行き届いていないということです。
ですが下水道の整備に関してもかなり地域差があります。都市部、特に日本人の方が住むような住居だと、下水に関して問題が起きることはまずありません。トイレやシャワーなどの生活排水が詰まって流れない事や異臭が漂うということもなかなか起こりませんし、詰まりを除去する商品もスーパーに売っているため問題ありません。つまり下水に関しても同様で、特に心配する必要もなく生活することができるということです。問題点といえばトイレの便座が冷たいことくらいでしょうか。
格差拡大の理由
ここまでインドの上下水道に関する整備状況を見てきました。その中で都市部では整備が進み、地方ではそうではないということをご紹介しました。ここまで整備状況に格差がある理由があります。
それは水に対しての日本人との意識の違いにあります。皆さん月末に生活費を払いますよね。生活費とは電気料金とガス料金と水料金のことです。つまりそれらを利用した分だけ料金を支払うわけです。これは日本では当然のことですよね。
ですがインドにおいて、とりわけ水に関してはそれが当たり前ではなくなります。つまり利用しても料金を支払わないということです。
現地の方は水を無料で利用して当たり前と思っており、水道料金を支払うシステムも浸透していません。水のATMがなかなか普及していないのもそのためです。特に地方ではそれ専用のポンプを使って、上水道から水を抜き取り利用するということが平気で起きています。これにより地方水道局では財政難が起きており、それが原因で整備の進行に遅れが出ているのです。無収水率が高くなっている原因の1つでもあります。つまり水道料金未払いや盗水による財政難を原因とする整備遅れにより、格差が拡大しているのです。
政府の取り組み

インド政府は15年前から水に関する整備を進めています
20世紀終わりごろからインドでは水の供給不足が顕在化してきました。インド政府は1990年代から2000年代にかけて416ダムを竣工するなどして対応してきましたが解決できていません。その原因は人口増加などに伴う上水需要の増加に対して、施設整備が追い付いていないことが挙げられます。下水に関しても同様で、都市部への急激な人口流入によって処理能力を超えた下水が排出されており、地域住民の生活環境が脅かされています。
インド政府は、2002年からの第10次5ヶ年計画において、十分かつ安全な飲料水の全国民への供給を唱えています。これを踏まえたうえで、政府は上水を水資源配分における優先順位のトップに置くことを示し、国民の生活を優先する姿勢を強調しました。
第11次5カ年計画においても、上下水道・の整備推進が言及されています。2011/12年までに都市部全人口への上水供給及び下水・衛生施設の提供を政策目標として掲げ、各州・自治体に対し開発計画を策定し、目標の達成を図るよう求めています。
第12次5か年計画に関しても同様です。政府はこの計画で実に88兆円に及ぶ額をインフラ整備に投資しています。もちろん上下水道整備も例外ではありません。さらに都市において生活用水の提供と下水管理を一体として考えるアプローチを始めるなど計10個の改革を行いました。
整備が進行しない理由
このようにインド政府は15年も前から上下水道に関する整備を進めてきているのです。インド政府が水整備を放置しているわけではないことがお分かり頂けたと思います。ですが上述したように整備が行き届いているとは言えない状況です。その理由は何なのでしょうか。
その原因は根本的に利用可能な水資源が不足していることが挙げられます。インドの人口は全世界の16%を占めていますが、その人口に割り当てられた世界水資源の割合は4%に過ぎません。さらにインドでは1日に400億リットルの水が汚染されているといわれており利用可能な水が慢性的に不足しているのです。そのためまずはダム建設など水資源確保に注力しなければならず、今まで上下水道整備まで手が行き届いていないのが現状です。また上述したように財源が不足しているのも事実です。これらの理由によりインドの上下水道整備が遅れているのです。
ここまでインドにおける上下水道の整備状況を見てきました。ではその整備はASEANの国々と比較してどのくらいの進行状況なのでしょうか。それでは見ていきましょう。
ASEANの現状
今回はマレーシアとタイを取り上げます。両国には多くの日系企業が存在しており、マレーシアには1,396社、タイには4,567社と両国ともかなりの数存在しています(インドは2016年で1,305社)。また平成26年の調査における在留邦人の数は、マレーシアには22,056人、タイに64,285人とこちらもかなり多いです(インドは9,147人)。そんな著しい経済の成長を遂げるASEANの一角を担い、日本とも関係の深い両国の水整備はどこまで進んでいるのでしょうか。両国ともインド同様、上水道と下水道に分けております。それでは見ていきましょう。マレーシアの現状

マレーシアの上下水道の整備状況を見ていきましょう。下の表をご覧ください。
上水道
| 上水道総延長 | 上水密度 (総延長/国土面積) | 上水道普及率 | 無収水率 |
| 11万㎞ | 0.35 | 90% | 37% |
下水道
| 下水道総延長 | 下水道密度 (総延長/国土面積) | 下水道普及率 |
| 1.3万㎞ | 0.04 | 67% |
上水道の総延長が11万㎞で上水道密度が0.35となっています。上水道の普及率は90%とかなり高い数値となっていますが、無収水率は37%とインドと同じぐらい高い数字となっています。
一方下水道総延長は1.3万㎞で密度は0.04とかなり低くなっています。インドと同じ数値となっていますが、国土面積がインドの10分の1ほどなことを考えると整備状況はまだまだのようです。また下水道普及率は67%です。地方では水洗のトイレが浸透していないことが、普及率が低い原因の1つではないでしょうか。
マレーシアでは2006年に「上下水道事業法の改正」を行い、水道事業の権限を州から国に移しました。これにより政府による統制的な整備が可能となりました。また12年には水資源の安全性、持続可能性、能力開発などのテーマを設定し、戦略的行動計画を実施しています。
タイの現状

タイの上下水道に関しても表にまとめてあります。ご覧ください
上水道
| 上水道総延長 | 上水道密度 | 上水道普及率 | 無収水率 |
| 10万km | 0.20 | 81% | 27% |
下水道
| 下水道総延長 | 下水道普及率 |
| データなし | 9% |
上水道の総延長は10万㎞、密度は0.20となっています。マレーシアとほとんど同じ上水道の普及率は81.9%となっています。8割を超える普及率ですが、都市部に偏った普及となっているようです。実際に都市部ではほとんどの場所で上下水道の整備が進んでいますが、地方ではほとんど整備が行き届いていないようです。また無収水率は27%となっており、まだまだ先進国との間には差があるようです。
一方下水道の普及率は9.6%となっており、このことからデータはありませんが下水道密度も低いということが考えられます。
タイでも水道水が直接飲めない状態にあり、整備がまだまだのようです。多くの地域では屋外に給水用のタンクがあり、そこに雨水をためて再利用している用です。今後10年間で9000億バーツ(約3.2兆円)規模の水関連開発が行われる予定です。最初の2年間で計2432億バーツ(8211億円)を費やし、地方の上下水道の整備などに順次着工する予定です。政府も積極的に整備を進めているようです。
インド マレーシア タイ 比較
上水道
| 上水道総延長 | 上水道密度 (総延長/国土面積) | 上水道普及率 | 無収水率 | |
| インド | 58万㎞ | 0.17 | 80% | 35% |
| マレーシア | 11万㎞ | 0.35 | 90% | 37% |
| タイ | 10万km | 0.20 | 81% | 27% |
密度
上水道密度に関してはどこの国もまだまだ低いようです。ただ、ASEAN両国の数値と比較するとインドの数値はそこまで低いものではないことが分かります。インドは国土面積が広いことも考えても単純に整備が進んでいないというわけでは無さそうです。さらに各国とも整備に積極的に取り組んでおり、5年後にはかなり整備が進むと考えます。
普及率
マレーシアの90%は高い数値ですがタイの81%ほどの普及に留まり、インドと大して差はありません。インドの80%という割合がそこまでものではないと分かります。3カ国とも都市部の整備が進み地方の整備がまだまだ行き届いていません。全国民が安全な水を利用できるのはまだまだ先になりそうです。
無収水率
3か国とも同じように高い数値となりました。やはり質の面でも整備が行き届いていないようです。ただ質より量が各国の課題である以上、まずは量の底上げに政府は力を注ぐのではないでしょうか。
下水道
| 下水道総延長 | 下水道密度 | 下水道普及率 | |
| インド | 16万㎞ | 0.04 | 30~40% |
| マレーシア | 1.3万㎞ | 0.04 | 67% |
| タイ | データなし | データ無し | 9% |
密度
インドとタイ両国とも同じようにかなり低い数値となりました。タイのデータはありませんが普及率から考えるに、密度もそこまで高いものではないでしょう。どの国も下水道のほうが整備が進んでいない傾向があるようです。インドだけでなくASEAN両国も下水道整備は進んでいないようです。
普及率
インドとマレーシアを比較すると差があるものの、タイの数値を考慮するとインドの整備がそこまでずば抜けて遅くれているというわけではなさそうです。
いかがでしたでしょうか。以上が3カ国のデータ比較です。インドの上下水道の整備がずば抜けて整備されていないというわけではありません。3カ国とも整備状況はあまり変わらないというのが結論です。インフラ面におけるインドのイメージは、ASEAN諸国に差をつけられているのが事実です。ですが実際にこうしてデータを用いて比較してみるとそこまで大した差ではないことが分かります。皆さんの知らないうちにインドのインフラはここまで整備が進んでいるのです!
まとめ
インドの上下水道整備はまだまだではあるものの、比較を通して見てみるとすごく遅れているというわけではないことをご紹介しました。安心してください、インドの水整備はASEANに負けていませんよ!インドのインフラ市場は年を追うごとに拡大しています。上下水道市場も例外ではありません。2010年時点で39億ドルだった市場規模は16年に64.6億円まで拡大しました。実に66%増という驚異的な伸び率です。私はこの市場の拡大により雇用が創出され、それがインドの経済成長を継続させる結果になると考えています。
インドでは現在官民が一体となって積極的に整備に取り組んでおり、その過程で生まれた労働力需要が新たな雇用を生み出しています。インドの労働人口は4.4億人とかなり多いですが、15歳以上の就業率は53%と低いです。残りの47%の人々が新たに製造業や建設業の職に就くことで所得も上がり、購買活動の活性化の伴う経済成長が実現されるわけです。
経済成長を継続させると考えたのは、これからもインドの上下水道市場規模は拡大の一途をたどると考ているからです。市場拡大が見込める要因は5つあります。
- 経済成長に伴う産業用水の需要拡大
- 老朽化した水インフラの再整備
- 新たな水インフラの建設需要
- 水・衛生関連サービス強化
- 環境問題、水の衛生状態に関する意識の高まり
これらから今後も上下水道市場が拡大し、それにより生まれた雇用が要因となり経済成長を継続するのではないかと考えます。
第4回目を迎えたこのシリーズもそろそろ終わりに近づいてきました。前回の電気編でも言いましたが、インフラが整っていないことはネガティブな面ばかりではありません!1つ1つ掘り下げていくとインドの新たな可能性が見えてきます。どうか広い視野でインドという国を見てみてください!
〈参考サイト〉
・https://www.toyoaquatech.co.jp/blog/2015/07/30/11
・http://diamond.jp/articles/-/30858
・http://www.mlit.go.jp/common/001131523.pdf
・http://www.mlit.go.jp/common/001057532.pdf
・http://www.mlit.go.jp/common/001131526.pdf